今年の富良野岳初冠雪は10月25日、平地の根雪まではまだしばらく過ごしやすい季節だ。紅葉と交えて美しい時でもあるが、収穫や畑終い冬支度と忙しくもある。

白菜やキャベツを作ってみた。大きく育ったが野菜が値下がりしているようなので、作りがいがない。かぼちゃも豊作だったが、オイラはかぼちゃとさつまいもはノドが詰まるし、どうも胃もたれするので食べきれない。

熊も多いが、それ以上に多いのが鹿さんたちだ。ファミリーで滑走路の草を食べに来る。草刈りの手間が少しでも省けるので歓迎します。窓を開けて呼びかけると、一瞬注目してくれますが、いつもの爺婆だと分かるとまた食べ続ける。
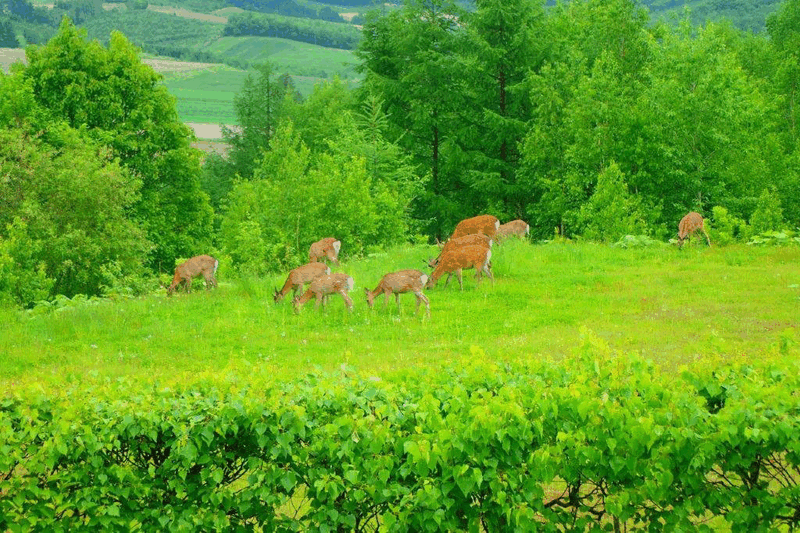
ドラム缶焼却炉の制作
燃料屋さんに貰ったドラム缶が余っていたので、焼却炉を作ってみた。コンクリート土管を使っていたが、大き過ぎたし蓋がないので火の粉が飛んで危険だった。
Youtubeでドラム缶の蓋を温存する方法が紹介されていたので真似てみた。
これは、ドラム缶の蓋と着火口兼灰取り出し口の蓋

側面から煙突を出すようにした。煙突が自重で倒れないよう溶接した。

煙突周囲を耐熱パテで埋める

底のロストル(火格子)は、レンガの上に溝の蓋(グレーチング)を斜めに切ったらちょうど1枚で間に合った。このグレーチングは歩道から取ってきたのじゃありません。以前に雑品屋(鉄屑屋)さんから貰ってきたものです。おそらく北海道では、除雪車等で道路脇の設備がよく壊され、雑品屋に集まってくるのではないかと思われる。

消化器を用意して試し焼。
煙突より火口からの煙の方が多いやんけ!Y(>_<、)Y ロストルの高さが低いせいかも? グレーチングに鉄筋を溶接して高くしたら改善できるかも知れない。

焼却炉が使えるのも、ぽつんと田舎暮らしの特権。
何を焼くかと言えば、得体の知れない病的作物(農薬を使わないので感染症や害虫が湧くことがある)や、廃棄リチウムポリマーバッテリー(リポ)である。リポはリチウムバッテリーの中でも発火・爆発しやすく、防爆缶に入れて保存しなければならない代物。通常塩水で処理し他の廃棄電池と同様に廃棄するのだが、とても手間がかかる。なので以前から焼いていた。当然爆発してしまうのであるが、安全に焼却すれば銅箔だけが焼け残る。あとは金属ゴミとして出せる。